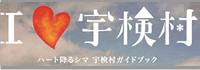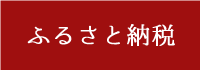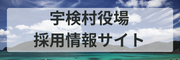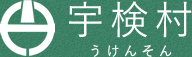ここから本文です。
更新日:2024年8月23日
宇検村農業委員会「農地の利用の最適化の推進に関する指針」
改訂 令和2年10月1日
策定 平成29年10月1日
宇検村農業委員会
第1基本的な考え方
平成28年4月1日に農業委員会などに関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の改正案が施行され、農業委員会においては「農地等の利用の最適化の推進」が最も重要な必須業務として明確に位置づけられた。
宇検村においては、農業の担い手不足と高齢化が問題となっており、それにむけた対策を図ることが求められている。また、本村の農業は中山間地で狭小な農地が多く、それぞれの地区によって農地の利用状況などが異なっているため、地域の実情にあった取組を推進し、それに向けた対策の強化を図ることが求められている。
以上のことから、地域の強みを生かしながら、活力ある農業・農村を築くため、法第7条第1項に基づき、宇検村農業委員会の指針として、具体的な目標と推進方法を以下のとおり定める。
なお、この指針は、令和5年度を目標とし、農業委員会と推進員の改選期である3年ごとに検証・見直しを行う。
また、単年度の具体的な活動については「農業委員会事務の実施状況等の公表について」(平成28年3月4日付27経営第2933号農林水産省経営局のうち施策課長通知)に基づく「目標及びその達成に向けた活動計画」のとおりとする。
第2具体的な目標と推進方法
1.遊興農地の発生防止・解消について
|
|
管内の農地面積 (A) |
遊休農地面積 (B) |
遊休農地の割合 (B/A) |
|---|---|---|---|
|
開始年の現状 (平成29年3月) |
166.1ha |
21.1ha |
12.7% |
|
中間年の現状 (令和2年3月) |
164.8ha |
27.4ha |
16.6% |
|
目標 (令和6年3月) |
161.1ha |
20.0ha |
12.4% |
注:「管内の農地面積」は奄美農林水産業の動向の耕地面積と利用状況調査1号遊休農地の合計面積
(2)遊休農地の発生防止・解消の具体的な推進方法
農地の利用状況調査や利用意向調査を通じて農地所有者に対する指導や説明、相談活動を実施する。
利用意向調査の結果を受け、農家の意向を踏まえた農地中間管理機構への貸付を推進し、遊休農地発生防止・解消を図る。
農業委員会や農地利用最適化推進委員による日常活動により、農地所有者の状況と農地の現状把握を行い、また、借り手農家の掘り起こしを図る。
利用状況調査と同時に実施する「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」によりB分類(再生利用困難)に区分された荒廃農地については、現状に応じて速やかに「非農地判断」を行い、守り活かす農地の明確化を図る。
2.担い手への農地利用の集積・集約化について
|
|
管内の農地面積 (A) |
農地利用集積面積 (B) |
集積率 (B/A) |
|---|---|---|---|
|
開始年の現状 (平成29年3月) |
166.1ha |
30ha |
18% |
|
中間年の現状 (令和2年3月) |
164.8ha |
62ha |
37.6% |
|
目 標 (令和6年3月) |
161.1ha |
75ha |
46.6% |
注)一年あたり農業委員1人20aの集積を目標に算出
(2)担い手への農地利用の集積・集約化に向けた具体的な推進方法
「人・農地プラン」の見直し作業等について、農業委員・推進員の立場で積極的に参画する。
農業委員及び推進委員は、農地の所有者と地域の担い手農業者の仲介役となり、農地中間管理事業を積極的に推進し、農地中間管理機構との連携強化を図る。
受け手となる担い手(経営体)の確保が重要であることから、担い手の経営改善の取組が円滑に推進するよう支援する。
3.新規参入の促進について
|
|
新規参入者数 |
新規参入者取得面積 |
|---|---|---|
|
開始年の現状 (平成29年3月)
|
1
|
0.3ha
|
|
中間年の目標 (令和2年3月)
|
1
|
0.3ha
|
|
目標 (令和6年3月) |
3 |
0.9ha |
注)新規参入者1人3000平方メートルの農地取得を目標に算出
(2)新規参入の促進について
村産業振興課、JA、県農政普及課等と連携して、新規就農者へのサポート体制の強化を図る。
行政機関等に対して、新規参入者が円滑に就農できるように支援・指導する体制の充実や行政機関等が独自に補助金・助成金を交付する制度の創設、新規参入者を促進する施策を提案していく。
後継者のいない農家や賃借可能な農地の情報を把握し、土地所有者の意向や希望に応じて新規参入者に情報を提供していく。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください