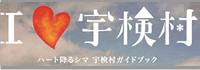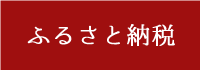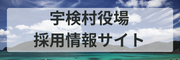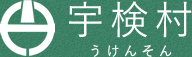ここから本文です。
更新日:2025年5月19日
令和7年度施政方針
はじめに
令和7年,第1回宇検村議会定例会の開会にあたり,村政運営に関する私の基本姿勢と,所信の一端を申し上げ,村議会議員並びに村民の皆様に,ご理解とご協力を賜りたいと存じます。
私は,村長就任6年目を迎えました。
これまで,所管の業務や災害対応等を通して,職責の重さを日々感じながら,村民の生命,財産,安全・安心な生活を守るため,職員と共に村政運営に取り組んでまいりました。
議会議員並びに村民の皆様には,ご理解,ご協力を賜りましたことに,心から感謝申し上げます。
私は,「さらに元気な村づくり」を基本理念に,2期目も,「宇検村(シマ)らしさ全開!」を掲げ,「稼げる産業の振興」,「快適な生活環境」,「健やかな暮らし」,「広がるつながり」,「心豊かな人づくり」を柱として,議会議員並びに村民の皆様の,ご理解をいただきながら,村民の声に耳を傾け,アンテナを張り様々な情報収集を行い,透明性がありスピード感のある村政運営に努めてまいりました。改めまして本村の発展のため全力で邁進することを,お誓い申し上げます。
今年度の施政方針も,私が公約した五つの柱と,第6次宇検村総合振興計画の,基本構想に掲げた六つの基本方針を軸に,基本的な考え方を説明させていただきます。
基本方針1
「きらりと光る稼げる産業を育むむらづくり」
持続可能な農林業の振興
本村の基幹産業である農業について,農業委員,農地利用最適化推進員,農地中間管理機構,宇検村元気の出る公社等と連携し,農地の確保・集積化を推進するとともに,遊休農地の解消を図り,農地の有効活用につきましても,令和6年度に策定した「地域計画」のさらなる充実に向け,「農地中間管理事業」を活用した農地の流動化や,「多面的機能支払い交付金」(水土里サークル活動)による,集落の環境保全などの取り組みを促進し,生産者の技術向上を目的に,定期的に各品目の講習会の周知や個別指導を行い,栽培技術や経営能力の向上を目指してまいります。
また,新規就農者の支援を拡充するため,認定新規就農者支援制度の検討を進めるとともに,初期投資や生活支援に対する補助制度の整備を目指してまいります。
さらに,農業支援対策として,園芸作物等のブランド協力金の助成を継続し,生産者の意欲向上とブランド化への参画を促進し,たんかんの選果場選果手数料の補助を通じて,生産者の経済的負担を軽減,初期生産コストの負担軽減を図ってまいります。
具体例としては,マンゴーの生産につきましては,新規栽培者への参入を支援し,農業用パイプハウスリース事業を拡充し,特に,気候変動による災害リスクを軽減し,生産の安定化を目指すため,引き続きリース料の一部助成を行ってまいります。
また,パッションフルーツにつきましては,苗木助成金の導入を行い,園芸作物の生産拡大と経営基盤の強化を図ります。さらに,とうきびにつきましては出荷助成金,収穫に係るハーベスターの大型機械使用料,運搬助成金を引き続き行うことで,面積,生産量拡大と,単収のアップを促進してまいります。
新規に,令和7年度から奄振事業を活用する予定です。奄美大島内の市町村と連携し「フルーツブランド化推進事業」を実施する予定です。特産品である,たんかんや津之輝等の特産品を中心に,KGAP取得に向けたブランド化を推進し,選果場の利用を促進するとともに,品質データを基にした改善提案を行い,生産量の安定化と高品質化を目指し,農家の経営安定とリスク軽減を図るため,自然災害や不測のリスクに備えた,農業共済制度の加入を促進し,農業者への制度説明会や,個別相談を実施して加入率の向上を目指してまいります。
次に,路地野菜等の生産者が,安定して出荷できる体制づくりを支援していくために,生産向上を目指した栽培指導の強化,販路拡大のための物流費補助の検討,また,地域住民との連携を深めるため,地産地消を促進するイベントや「ケンムンの館」の活用を推進してまいります。
次に,令和10年度,新規採択予定の中山間地域総合整備事業については,令和2年度から行いました「ふるさと探検隊」,「地域支援事業」による,各集落,各校区でのワークショップでの要望事項や,農業委員の農家への聞き取りの成果の実施に向けて,地元説明会や事業への地元合意形成を図ってまいります。
令和5年度に試験的に実施したそば栽培については,検証成果を基に,秋まき品種を活用した栽培の現地適応性を,引き続き検証します。これにより,栽培面積の拡大や安定供給ができるようにし,地域農業の新たな柱としての基盤構築を目指します。
また,農作物への被害軽減を目的とし,効果的な鳥獣被害対策を講じます。現在実施している,資材購入費助成金による補助に加え,県の鳥獣被害交付金を活用して,カラス箱罠を新たに設置し,被害の抑制を図り,併せて,捕獲活動の効率化を進めるため,地域住民や猟友会との連携を強化してまいります。
「宇検村元気の出る公社」は,地域の農業振興や環境保全,雇用創出等において欠かせない存在であり,今後も,その存続価値は大きいと考えられます。しかし,持続的な運営を行うためには,作業の効率化や経費削減,堆肥の販売価格,さらに農機具使用料の見直しを行い,持続可能な経営努力を継続することが不可欠と考えられます。
公社の活動をより効果的にするために,村としても適正な管理受託のあり方を検討してまいります。
次に,畜産事業については,令和8年度に実施予定の畜産クラスター事業において,鶏舎の造成・増設や肉用牛生産農家への大型機械導入に向けた検討を進め,畜産農家への支援体制を強化します。これらの取り組みにより,飼育規模の拡大と生産効率の向上を図り,地域畜産業の競争力を高め,安定した収益基盤の確立を目指してまいります。
次に,森林資源は本村の重要な財産であり,地域の自然環境や景観の保全に寄与するとともに,産業資源としての役割を担っています。
令和7年度も,森林資源の持続的な利用を図るため,森林再生事業を推進し,世界自然遺産登録後の地域として,環境に配慮した森林整備や保全活動を継続し,地域の森林が持つ多面的機能を活用します。
また,森林環境贈与税を有効活用し,地域の森林管理体制の強化や環境教育への取り組みを進めてまいります。
また,令和7年度より,「かごしま林業大学」が創設され,地域の林業を支える労働者の育成を目的に,技術指導や研修を行い,林業労働の魅力を発信し,地元の若者を中心に新規参入者を増やすための施策を展開します。
本村も県や関係機関と連携し,次世代に向けた持続可能な森林づくりを実現し,地域経済の活性化と林業の基盤強化を図ってまいります。
焼内の海で輝く活力ある水産業の振興
やけうち湾の水産資源を活用し,漁業者の経営安定を図り,離島特有の高輸送コストが課題となる中,輸送コスト補助事業を活用して生産性向上を推進し,水産物の販路拡大を図り,地域産品の競争力向上を目指してまいります。
また,湾内の漁場環境を整備し,水産資源の保全と持続的利用を図り,増殖場2か所の設置を実施し,漁場の生産性向上を目指してまいります。
さらに,海洋汚染防止のため,湾内の清掃活動や環境保全啓発活動を,地域住民や漁業関係者と連携して推進してまいります。
地域の連携が育む商工業の振興
昨年度は,5年ぶりに宇検村やけうちどんと祭りが,開催されました。引き続き,令和7年度も11月開催の秋祭りとして宇検村商工会を中心に盛大に開催する予定であります。
また,宇検村観光物産協会とタイアップし,造成された体験メニューを販売し,宇検村交流人口の拡大と,観光産業発展の相乗効果を図ってまいります。
11月第一日曜日と固定して毎年開催することにより,郷友会や同窓会など,どんと祭りが帰省のきっかけの位置づけとなり,村民が集うイベントになるよう,関係団体との連携を強化してまいります。
商工業の振興については,物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し,プレミアム率を前年度より上げた「どんと券」を,4月から販売できるよう準備を進めてまいります。
広く村民へ利用していただくために,令和6年度から販売元や利用期間を変更し実施しましたが,村民からの意見要望を踏まえながら,更に利便性の良い商品券の発行に努めてまいります。
また,農林水産物等輸送コスト支援事業については,県本土との流通条件不利性を改善し,生産・産業振興の推進を図るため,奄美群島振興交付金を活用し,農林水産物や加工品(黒糖焼酎等)の輸送費補助を継続してまいります。
人口が減少する中,働き手不足の常態化を解消するため特定地域づくり協同組合,「結いワーク宇検村協同組合」
が,令和6年度設立されました。
現在事務職員と,働き手の2名体制の組合ですが,安心して仕事に従事できる環境を広くPRし,定住人口の増加・人口流出の抑制・安定した働き手の確保を目指してまいります。
宇検村の自然と歴史を伝える観光振興
宇検村観光基本計画のモットーである,「風に触れ,土に触れ,人に触れ,五感で感じる心旅」を展開するため,宇検村観光物産協会では,年間を通して様々な仕掛けを繰り広げております。
村内での宿泊や観光,農業や漁業体験などを組み合わせた,体験型観光メニューも造成しており,宇検村元気の出る公社旅行部門の開所により,ツアーを販売することが可能になったため,観光組織や事業者等と連携し,宇検村オリジナルツアーの販売に力を入れてまいります。
世界自然遺産登録で追い風が吹く中,奄美大島へ来島する観光客をはじめ,島内の方もターゲットとし,観光促進をとおして,経済活性化や関係人口の拡大に向けて取り組みます。
暮らしと文化そのものが,地域の宝・地域資源となり,観光産業の一端となりながら,地域の暮らしや文化が先々も継続していけるよう,観光による地域づくりに努めてまいります。
基本方針2
「快適な生活を支えるむらづくり」
合理的な土地利用の推進
令和7年度も,現在進めている芦検地区を中心に地籍調査事業を継続し,地権者間の合意形成を支援し,住民説明会を通じて調査の重要性と進捗状況を共有してまいります。
また,引き続き航空レーザー測量技術を活用して,山間部やアクセスが困難な地域の,測量作業を迅速に進めるとともに,全体事業の期間短縮を図り,地域住民の財産権保護や公共事業の円滑化に寄与し,地域社会の発展に資する取り組みを継続してまいります。
交流を促進する交通基盤の整備
社会資本整備を進めていくことにより,現在だけでなく未来にわたり,本村の「安全・安心の確保」,「持続可能な地域社会の形成」,「経済成長の実現」を達成し,その先には「真の豊かさ」を実感できる村を構築できるよう,計画を着実に実施してまいります。
まず,県道整備については,村内の3集落を結び主要地方道名瀬瀬戸内線につながる重要路線であるため,土砂崩壊による交通途絶の防止,見通し不良個所の解消,地域住民の安全を確保するため,一般県道曽津高崎線・平田工区の改良工事を継続して整備してまいります。
今後の計画として,道路交通の安全確保や,交通規制の解消を図るため,阿室工区の整備,また,線形不良や幅員狭小による大型車の離合困難,土砂崩壊による交通途絶を防止するため,生勝工区の整備を行う予定であります。
主要地方道,湯湾新村線・赤土山工区については,整備による改変が大きいことと,多額の事業費を要することや,世界自然遺産区域内の整備となることから,特に自然環境に配慮する必要があることが課題となっており,国道58号を補完する代替道路・緊急輸送道路としての機能や,物流活動や地域間交流の活性化及び,希少動植物保護の観点からも,新たなルート案(トンネル化)の検討も含め,環境と生態系に配慮しながら,早期完成を目指し県及び関係機関に強く要望をしてまいります。
その他の県事業については,砂防事業(土石流対策)では,久志川,名柄川を引き続き整備し,地滑り対策事業で,湯湾地区を計画しています。急傾斜地崩壊対策事業では,久志1地区,芦検池城地区,下朝戸地区を継続事業で整備してまいります。
村道整備については,地域住民や観光客が安全・安心に利用ができる道路空間の確保を目指すと同時に,災害時の迂回路としての機能も図れるよう,国庫補助事業で引き続き,宇検船越線・屋鈍曽津高崎線の改良工事を行ってまいります。
また,老朽化し通行に支障のある,舗装路面や,腐食し機能が低下している安全施設の維持を図るため,赤土山線・田検名音線の維持補修工事を行います。
橋梁に関しては,業務委託にて点検を行い(修繕・更新・撤去)を検討し,利用者の安全確保が図れるよう,計画的に整備してまいります。
村単道路整備については,走行時の安全確保のため,区画線の修繕工事や,災害時の避難・迂回路機能確保のため補修工事を行います。また,高潮時の冠水対策や,緊急車両通行道路の整備工事を,継続して名柄集落で進めてまいります。
港湾整備については,継続して,湯湾港(須古地区)の岸壁補修やエプロン舗装を行い,老朽化対策による施設の延命化と機能回復を図り,建設資材等の安定供給確保に努めてまいります。
漁港整備については,継続補助事業により,宇検漁港海岸保全施設長寿命化計画に基づいた,老朽化施設の延命化,機能回復整備を行ってまいります。また,未指定漁港(生勝地区)の係留施設修繕工事を行い,利用者の安全確保に努めてまいります。
河川整備については,河床低下による護岸背面の吸い出し防止対策工事や,護岸補修工事,管理道路舗装工事を,村内10河川で行い,農地利用者や近隣住民の安心・安全に繋げてまいります。
公共機関の維持と利便性の向上
公共交通の利用者及び担い手の減少が進んでいる中,公共交通機関の確保・維持に取り組むため,令和6年度に,奄美大島地域公共交通計画を,広域と各市町村で策定しました。地域公共交通は,移動のための手段ではありますが,教育や医療福祉,観光など様々な分野に関係し,村民の暮らしを支える土台となっております。
村内で運行している,屋鈍線と宇検線の2路線に加え,湯湾管内のマジンスローカーの運行のみでは,村民のニーズに対応できていないため,本村の公共交通の課題解決に向け,取り組んでまいります。
村内にある既存の組織,団体等が参画した連携・協働の取り組みを進め,村民が村内公共交通を担える仕組みづくりを,検討してまいります。
高校生通学バス助成金につきましては,定住,U・Iターンの促進及び,地域公共交通機関利用の促進を図るため,通学バス利用料及び,帰省等のバス利用料の助成を引き続き実施してまいります。
利便性を高める情報通信技術の活用
デジタル社会への移行は,住民生活の快適さを伴うことが必須であります。住民への情報発信は,防災無線に加え公式LINEの充実と,利用者拡大を図ってまいります。避難所において情報が送受信できるよう,各集落公民館にWi-Fi整備を行います。健康体操,健康教室や郷友会とのイベントなど,日常生活での利用も期待され村民福祉の向上が図られます。
令和7年度も,適宜地域に合った機器やシステムを導入し,住民サービスの向上に努めてまいります。
業務においては,6年度末から勤怠システムを導入しており,引き続き電子契約,電子決済など業務のスマート化を進め,職員間の情報共有による効果が,住民サービスの向上につながるよう努めてまいります。
快適な生活をつくる住環境の整備
住居不足の状況を打開する施策として,宇検村民間賃貸住宅補助金制度を制定し,公募をかけたところ,賃貸住宅4戸が建築され,令和7年4月から運用が開始される予定となっています。新築された住宅は,宇検村の定住促進や人口増加に繋がり,地域の活性化が図れると期待しております。
また,定住促進空き家活用事業による,空き家の改修についても,3件を見込み予算を計上しております。
一方,防災・衛生・景観など周辺環境に悪影響を及ぼす,危険廃屋の撤去については,土地や家屋の未登記や相続の問題など,村の施策では解決できない壁がありますが,法務的手続き事務作業を進め,急を要する物件に対し行政代執行が講じられるよう,努力してまいります。
公営住宅の整備については,宇検村公営住宅等長寿命化計画に基づき,公営住宅ストック総合改善事業として年次的に住宅廻りの外壁や,屋上防水の修繕等を計画的に実施し住環境整備に努めてまいります。
本年度は,須古美長良住宅2号棟を整備いたします。
良質で衛生的な生活環境づくり
簡易水道事業については,前年度に引き続き,湯湾地区の本管布設工事及び湯湾・須古・石良地内の宅内引込み工事と湯湾浄水場・部連配水池の機械設備更新を行い,安全で安心な生活用水の供給に努めてまいります。
ゴミ処理につきましては,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため,適切な方法で処理を行います。また,ごみの減量・リサイクル化を推進するために,家庭用ごみ処理機の購入費補助,ごみの分別や,適切な出し方等について普及啓発に取り組んでまいります。
合併浄化槽設置の推進につきましては,家庭から排出される,し尿及び生活雑排水による,公共用水域の水質汚濁を防止するため,国・県の補助事業も活用して,合併浄化槽の設置の促進に取り組んでまいります。
集落排水事業は,住民の生活環境の向上と地域資源の保全に欠かせない,重要なインフラ整備の一環であります。施設の老朽化対策や,事業の効率化を進めることで,持続可能な運営体制を確立し,地域の快適な生活環境を守るため,継続して事業を推進してまいります。
農業集落排水事業では,芦検処理施設の機器類の更新と,湯湾地区と田検地区の統合に向けての,調査測量を行います。
漁業集落排水事業では,令和7年度より施設の更新事業が採択され,本年度は事業実施に向けた実施設計を進め,水質浄化機能の向上を目的とした最新設備の導入を検討し,地域の環境保全に寄与してまいります。
昨年度から,移行された公営企業法会計では,財務状況の的確な把握と効率的な事業運営を進め,収支バランスを考慮しつつ,住民負担を抑えるための料金体系の見直しを検討し,持続可能な運営体制を確立するために,専門家や関係機関の協力を得て,管理業務の効率化を図ってまいります。
安心・安全な地域社会づくり
自然災害時の被害発生を軽減するため,河川護岸等の整備も柔軟に対応したいと考えております。
村内県道の維持管理につきましては,権限移譲交付金で除草,路傍樹管理を実施してまいります。
村内の県道,村道の除草等維持管理については,民間事業者と,元気の出る公社への業務委託により,除草,路傍樹管理,交通に支障のある枝木の排除を,適正に実施してまいります。
地域防災力の強化
村民が安心して暮らせる村づくりは,最も重要な施策の基本とするものであり,自助・共助の意識向上を図るための,自主防災組織の充実と活動への支援として,研修機会や防災備蓄品などの公助に努め,連携して地域防災力の強化を図ってまいります。
また,昨年1月の能登半島地震以降,日向灘においても震度6弱,震度5弱と2回比較的大きな地震が発生し,南海トラフ地震も心配されます。防災訓練も,台風,大雨想定に加え,今年も地震津波想定の訓練も行ってまいります。避難所体制も,Wi-Fi整備を行い情報共有に,努めてまいります。
交通安全・防犯体制の充実
交通安全,防犯体制につきましては,村内を巡回する青色回転灯パトロール車両が9台と充実し,村内の危険箇所改善に貴重な意見が反映されております。
今後も,宇検村安心安全まちづくり推進協議会との連携を,図ってまいります。
そのほか,災害対応,防災対策には消防職員,団員の統率のとれた体制が必須であり,今後も,資質向上のための研修受講を,より充実かつ積極的に行ってまいります。
基本方針3
「魅力あふれる「人と自然」が調和するむらづくり」
豊かな自然環境を次代につなぐ地域社会
ゴミの不法投棄対策につきましては,年間を通して村内の林道や,主要道路沿いなどのパトロールを行うことにより,不法投棄の抑制に努めてまいります。
海岸漂着物対策事業につきましては,国の補助を活用し,海岸漂着ゴミの回収,処分を行うことにより、海岸の景観・環境保全に努めてまいります。
ノネコ・ノラネコ対策事業につきましては,今後も村内に生息する希少種を守るために,ノネコ・野良猫の減少を目的とした事業を,関係自治体・関係団体と連携して推進してまいります。
飼い猫につきましては,適正飼養,動物愛護の意識の向上,自然環境及び生態系の保全を図ることを目的とした,不妊手術やマイクロチップ装着の助成を継続し,村内のノネコ・野良猫の発生源対策に努めてまいります。
人と自然が共生する未来の,宇検村を実現するため引き続き,里海づくり事業を展開してまいります。シマの暮らしを支える自然環境は,気候変動と生物多様性の損失という,地球規模の課題に直面し,宇検村の海も,かつての豊かさを失っています。シマの暮らしが豊かになる里海づくりが,あわせて社会的課題の解決になるよう,1.生物がたくさんいる海(自然環境),2.人が集まる海(人口・経済),3.怖くない安心・安全な海(防災・気候変動)の3点を方針に,広く村民の声を反映しながら,海域管理計画の策定を進めてまいります。
村の宝である人と自然が輝く交流
令和7年10月に,宇検村で国際サシバサミットが開催されます。サシバの越冬地である,奄美大島の環境は,獲物が潤沢に存在する豊かな環境であることを証明し,自然環境の指標となっています。
サシバの保護や,生息する自然環境の保全など,共有する自治体や,国が一堂に会する国際サシバサミットは,奄美大島宇検村の価値や知名度を,世界に発信する絶好の機会ととらえています。村民をはじめ,奄美大島全市町村の協力を頂きながら,国際サシバサミットの成功に向け取り組んでまいります。
村の,最上位の計画である「第6次宇検村総合振興計画」と,国の総合戦略の整合性を図りながら策定を進めている,第3次宇検村まち・ひと・しごと創生総合戦略が,3月中に完成する予定です。宇検村における人口減少と,村の衰退に歯止めをかけ,地方創生を目的とした実行型の計画の実現を目指し,新たにプロジェクトマネージャー制度を導入いたします。
地域,民間,行政等を繋ぎ実質的にプロジェクトをマネージメントする人材の確保と,産学官協定を締結している日本航空(JAL),上智大学,伊藤忠商事の人的・物的資源,各専門性も事業執行に活かしながら,村民の豊かな暮らしのために,第3次総合戦略を着実に進めてまいります。
また,現在の地域おこし協力隊制度も活用しつつ,併せて,3カ月以内の短期間,地域で活動する地域おこし協力隊インターン制度を活用し,地方移住や定住という目的ではなく,一時滞在し地域活性化や課題解決に参加できる,学生や若者をキープできる仕組みづくりに,努めてまいります。
毎年実績を伸ばしている,ふるさと納税につきましては,新たな事業所や農家等の参入と,返礼品の拡大を更に図りながら,納税者の「志」に応える施策に活かしていけるよう,事業の充実に努めてまいります。
共生・協働で魅力ある地域社会づくり
誰もが安心・安全に夢や希望をもって,多様な生き方を選ぶことができる地域づくりを目指し,村内小中学校へ専門の講師を派遣し,学び合い事業を展開いたします。
併せて,該当校区の地域の方々も対象として実施し,人権・ジェンダー平等の理解と,その意識の根付いた地域づくりを促進してまいります。
人権啓発活動の推進については,各関係機関と連携し,人権問題についての理解を深め,人権の尊重されるむらづくりに努めるため,特設人権相談所開設等,継続した人権啓発活動に取り組んでまいります。
宇検村内で,外国人労働者を確保する事業者が年々増加している現状をふまえ,多文化共生社会の実現に向け,取り組んでまいります。外国人住民が,村内で安心して仕事と生活ができるよう,平等な社会参画や情報が提供できる,環境づくりに努めてまいります。
基本方針4
「健やかでぬくもりのある支えあいのむらづくり」
みんなで支えあう地域福祉の充実
村民が互いに支えあいながら,安心して暮らすことができる地域共生社会を実現するため,令和7年3月末に策定される『宇検村地域福祉計画・地域福祉活動計画』を基に,行政・社会福祉協議会・その他関係機関との連携を図りながら,地域福祉の推進に努めてまいります。
健康で安心して暮らせる予防・医療の充実
感染症対策については,新型コロナ感染症や,季節性インフルエンザ等の定期接種を積極的に実施し,国や県と連動し,対策をしっかりと講じ,村民の安心と安全が図られるよう,取り組んでまいります。
保健事業につきましては,宇検村健康増進計画「第2期いきいき健康うけん21」,「国保データヘルス計画」,「後期高齢者データヘルス計画」に則し,本村の健康課題であります,脳卒中を含む循環器疾患予防を,推進してまいります。
令和6年度から開始された,「第2期いきいき健康うけん21」では,特定健診受診率・特定保健指導の実施率向上,生活習慣病の重症化予防,1人あたり医療費の抑制などを主な取り組み計画としております。
国保保健事業,高齢者の保健事業と,介護予防事業を一体的に実施し,村民が自ら健康づくりに取り組めるように支援し,健康寿命の延伸・QOL(生活の質)の向上を目指してまいります。
特定健診・長寿健診・各種がん検診受診率の向上,各種予防事業について,受診しやすい環境整備を行うとともに,特に,若年世代から健診受診・運動習慣の継続など,発症予防に力を入れて,取り組んでまいります。
国保施設事業につきましては,令和6年12月に完成しました新診療所において,診療機器の整備を行っており,関係医療機関との連携強化を図り,住民への健康・医療・介護サービスの向上に向けた医療機能強化と情報連携を積極的に行い,住民が安心して暮らせる村(シマ)づくりを目指します。
未来を育む子育て支援の充実
妊産婦,子育て世帯,子どもを誰一人取り残すことなく,切れ目のない相談支援体制の充実を図るため,母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行う,「こども家庭センター」の開設に向けて,体制整備を行ってまいります。
併せて,令和6年度から配置している,こども支援コーディネーターを中心に,地域・行政・学校を繋ぎ,きめ細やかな支援体制の強化に努めてまいります。
令和7年3月末に策定される「第3期宇検村子ども・子育て支援事業計画」に基づき,子育てを社会全体で支援する総合的,計画的な施策を推進してまいります。
令和7年度から,新たに次世代の担い手となる人材育成一環として「可愛しゃんくわぁまがぁば旅すむろ」プロジェクトを進めてまいります。このプロジェクトは,早い段階から様々な職業に触れ,見識を広げることで子どもたちが夢や希望を持てる,体験や自分の将来像を描く上で刺激となる機会の,提供ができるよう努めてまいります。
いきいきと暮らせる高齢者福祉の充実
高齢者福祉についてですが,現在,『美人草』グループの活動が注目を集めています。高齢者の方々が歩んできた,これまでの人生経験を活かしながら,生きがいや喜びを感じることのできる場や活動を,今後も支援してまいります。
また,グループポイント事業等を利用し,高齢者が支え手となる活動への参加促進や,生涯学習等の視点を含めた高齢者の社会参加機会の確保,交流の場をつくり,高齢者の介護予防を促進いたします。
村内に居住する高齢者に対し、長寿を祝福し、健康で楽しく生活できるよう、敬老年金の支給、バスの無料乗車券の交付を引き続き実施してまいります。
介護保険事業につきましては、「第9期介護保険事業計画」を基に、どぅくさ体操等の通いの場,通所型サービスC,訪問型サービスCを中心とした,予防施策を引き続き重点的に進めていくと同時に,買い物移動といった,生活支援の体制づくりに取り組んでまいります。また,団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年には,要介護認定者数の増加が見込まれています。2040年を見据えた,村の介護保険サービスの在り方についての検討も,行ってまいります。
自分らしくを支える障がい者福祉の充実
令和6年度から,令和8年度までの3か年計画として策定された,「障害者計画」,「第7期障害福祉計画」,「第3期障害児福祉計画」をもとに,障害福祉サービスの充実を図ります。
障害のある方が,居宅介護や生活介護を利用しながら,住み慣れた地域で,地域との関りを持ちながら,自分らしく安心して暮らせる環境づくりに,努めてまいります。
障害を理由とする差別の禁止,地域社会における共生,障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援,アクセシビリティの向上,総合かつ計画的な取組の推進を基本的視点とし,本村に住む人々が,生きがいと楽しみのある生活を送り,一人ひとりが尊厳を持ちながら,いきいきと住み続けられる村づくりを推進してまいります。
自立に向けた社会保障の充実
生活困窮者への自立を支援するため,各種制度の適正な運用,周知を図り,各関係機関と連携を取り,困窮状態に至る前段階からの支援に努めてまいります。また,生活困窮者・世帯には,健康面での不調を抱えるケースも多いことことから,専門職による予防的な介入にも,努めてまいります。
基本方針5
「ふるさとを愛し、未来へはばたく心豊かでたくましい人を育むむらづくり」
生きる力をはぐくむ学校教育の推進
令和7年度におきましては,「宇検村教育振興基本計画」に基づき,「ふるさとを愛し,未来(あす)へはばたく,心豊かでたくましい人づくり」を,教育行政推進の基本目標とし,その推進については,「ふるさとの豊かな風土や教育的な伝統を生かし,ふるさとに立つ教育」を視点として,引き続き取り組んでまいります。
学校教育におきましては,「生きる力を備えた元気な宇検村の子どもの育成」を目標とし,村内の児童生徒それぞれに密着した学習指導や道徳教育,生徒指導,人権教育,読書活動等を推進するとともに,教育相談員・スクールソーシャルワーカーの活用や,いじめ防止基本計画に基づいた対策を推進してまいります。
また,児童生徒の健やかな成長のために学習者主体の授業や部活動,一校一運動の実践,食育など一層の充実を図り,学校給食の無償化及び各種大会出場への助成も引き続き継続してまいります。併せて,防災・安全に関する指導の充実・危険予知・回避能力の育成・防災訓練等の実施・各教科等における安全指導の充実にも努めてまいります。
なお,中学校の部活動につきましては,国の提言等を踏まえ,土曜・日曜の活動を地域へ移行する準備を昨年に引き続き進めてまいります。
本村の児童生徒の学力は,今年度の4月に小学6年生,中学3年生を対象として実施された全国学力・学習状況調査の結果において,小学校は,実施教科である国語・算数に関して,県平均をともに上回る結果となりました。一方で,中学校は,実施教科である国語・数学ともに,県平均を下回る結果となり,学年間による学力の差に課題も見られます。
その課題解決のため,村教育研究会による教職員の研修会や,各学校における校内研修会等を実施し,複式・少人数クラスにおける個別最適な学習の充実を図ってまいります。
また,令和7年度は,すでに整備されておりますタブレット端末機の更新時期となっており,「児童生徒一人1台のタブレット端末」の有効活用も引き続き図ってまいります。
併せて,昨年度の小学校に続き,令和7年度は中学校で使用される教科用図書の改訂に伴い,デジタル教科書を導入することで,「主体的・対話的で深い学び」の更なる推進を図ってまいります。
また,日常の学校生活に困り感をもっている,児童生徒に対する特別支援教育支援員による支援,英語教育小学校専科指導教員及び英語指導助手(ALT)の活用による外国語教育の充実,「奄美大島,徳之島,沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録を契機に開催しています,「やけうちっ子環境学習・世界自然遺産博士講座」も,引き続き取り組んでまいります。
体調不良など,やむを得ず学校に登校できない児童生徒に学びの場を確保し,家庭学習など自主的に学習を促進するため,タブレット端末の持ち帰りも引き続き進めてまいります。
さらに,学校における教職員の働き方改革を推進するため,令和4年度に校務支援システムを導入しており,システムを活用することで,教職員の校務負担軽減を図ってまいります。
併せて,施設の整備や点検補修,学校緑化に努めるとともに,児童生徒減少対策については,名柄校区・阿室校区活性化対策委員会と連携を図りながら,親子山村留学制度を継続して推進してまいります。
また,田検小中学校の共同調理場や,各併設校の調理場の今後についてですが,令和3年度の「学校給食のあり方検討委員会」において,検討協議の結果,建設候補地の選定と,総合給食センター方式での整備を進めていく方向での,検討結果の報告がありました。よって,令和6年度より,給食センター建設のため建設予定地の地質調査が終了しております。また,令和7年度に関しましても設計委託を予定しており,給食センター建設へ向けての準備を進めてまいります。
多様なニーズに応える社会教育の充実
次に,社会教育と社会体育についてですが,「結いの心で生き生きと学ぶ活力ある宇検村民の育成」を目標として,令和7年度においては,主に次の事業等に取り組んでまいります。
まず,令和5年度より村誌「民俗編」の編纂業務を再開しており,令和9年度を完成の目標として,取り組んでおります。
日頃から,宇検村を元気づけるために取組や活動を行っております,宇検村連合青年団の活動等についてですが,令和4年度からの取り組みとして,「地域食堂(子ども食堂)・マリンスポーツ体験・スマブラ大会・グルメフェス・各集落支援(豊年祭支援)」を実施しておりますが,今後も,このような村連合青年団の取組・活動に対しまして,村としましても,引き続き支援をしていきたいと,考えております。
さらに,継続的な取組として,今後の児童生徒の成長を見据え,家庭教育や家庭教育学級の充実,PTA活動や子ども会,社会教育関係団体の活動の充実を図り,子育ての機運醸成に努めてまいります。さらに,村民が継続的に学ぶことのできる,公民館講座や図書室などの充実を図り,村民の利用促進を図ってまいります。
また,児童生徒の健全育成事業につきましては,宮城県七ヶ宿町との相互交流事業です。昨年の夏には七ヶ宿中学校の1・2年生を受入れ,12月に宇検村の中学1年生を派遣することができ,スキー体験等を通じて七ヶ宿中生徒との交流を,深めることができました。引き続き中学1年生を対象として,継続して事業を実施してまいります。
また,沖縄県との「平和交流事業」につきましても,令和4年度から,近隣の瀬戸内町と大和村も加わり,児童生徒を対象に今年度で5回目の「平和交流事業」を実施することができました。悲惨な戦争のことを学びながらも,交流を通して関係を深めた子供たちに改めて平和学習交流事業の大切さを感じました。
今後とも,幅広い年代で平和交流の輪が広がるよう,取り組んでいく考えであります。
また,子ども達が英語を自然な方法で学び,コミニュケーション能力を育むことを目指し,むづかしい発音を早い段階で習得して,楽しく実戦的に学習することを目的に,乳幼児が,言葉を覚えるのが2歳から3歳と想定されることから,村内の保育所の年長組から小学校3年生ぐらいまでに,生の英会話に触れさせることで,より早い英会話ができるよう,ウケンキッズイングリッシュを昨年に引き続き実施してまいります。
レッスンは100パーセント英語で進め,体を使ったアクティビティやジェスチャーを活用し,子ども達が直感的に英語を理解できる環境を提供し,子ども達が講師と一緒に楽しく学んでいけるよう,雰囲気を大切にしながら,基本的な英語スキルを身につけられるレッスンです。
このプログラムを小学3年生まで続けることで,子ども達は英語を自然な形で習得し,将来の学習に対する意欲を育み,本村ならではの英語教育を進めてまいります。
その他の事業では,中学三年生のテーブルマナー教室や,茶道教室・新春書初め会,やけうちっ子体験チャレンジスクールや,一般社団法人アスリートネットワーク「つなGO奄美大島」事業と,連携したスポーツ教室の実施などについても,引き続き実施をしてまいります。
つぎに,生涯スポーツを通した健康づくりと仲間づくりを推進するため,令和6年度に,宇検村陸上競技場大規模改修事業として再整備を行いました,村陸上競技場も完成が近く,令和7年度には,5年振りとなります村民体育大会も開催する予定にしています。
また,引き続き再整備検討委員会では,運動公園全体の再整備計画につきましても,今年度以降も協議を重ねていただき検討結果の報告をおこなっていただきたいと考えております。
健康づくりや仲間づくりを促進する生涯スポーツの推進
村体育協会を中心とした社会体育推進体制の整備を進め,来年度,本村で開催される,県体大島地区大会バレーボール男子競技と,大島地区スポーツ少年団剣道競技の大会運営につきましては,各競技団体と連携を図りながら,大会運営の準備を進めてまいります。
スポーツ少年団の健全育成,毎週月曜日夜間の体育館無料開放も継続してまいります。
さらに,スポーツ推進委員や関係団体などの協力を得ながら,村内の社会体育施設の点検を実施し,事故防止に努めながら効果的な活用を進めてまいります。
併せて,高校生・大学生などのスポーツ合宿誘致についても引き続き推進いたします。
次代につなぐ地域文化及び芸術活動の振興
続いて,「地域文化及び芸術活動の振興」については,今後も文化協会や公民館講座の講師の先生方と連携を図りながら,文化芸術活動の普及・振興に努めてまいります。
文化財保護につきましても,今後も有形・無形文化財についての,保存・継承を推進してまいります。
宇検村振興育英基金につきましては,奨学金貸与事業を引き続き実施し,必要に応じて学校教育,社会教育,文化,体育事業への助成なども検討してまいります。
基本方針6
「村民とともに、力強い自治をつくるむらづくり」
時代に対応した行政運営と人事管理
法改正や国の施策など,時代に対応した弾力的な行政運営を行っていくためには,業務の量や働き方など職員の適切な配置が必要であります。WEB勤怠管理システムの導入により,時間外勤務の管理や事務分掌の見直しを行い,職員の健康管理を進めてまいります。
定年延長により,職員の年齢構成に偏りが生じないよう,適宜職員採用を実施し,年齢構成の平準化を進めます。
令和5年度から,DX部署を設け職員の業務のスマート化に取り組んでいます。会議システムや勤怠管理システムによる,ペーパーレス化と庁内のスピーディーな事務処理を目指します。役場全体の徴収事務において,コンビニ収納できるように取り組んでまいります。
住民の声,要望に応えるだけでなく,行政需要を的確にとらえるために,積極的に村民とのコミュニケーションを図ってまいります。
そのうえで政策立案から,予算化まで総合的に行動できる職員として,資質向上を図るため外部機関とも連携した職員研修を実施してまいります。
財政の健全化
国の経済活動は,雇用・所得環境の改善が続き,個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど,緩やかな回復が続いています。この景気回復過程での,国の税収増加により,年々地方交付税も増加していますが,物価上昇による工事費の増や,人件費,委託料,旅費等経常的経費の歳出も増加しています。
こうした景気回復の傾向を歓迎するも,地方税など自主財源や地方交付税などの,依存財源の大幅増加は見込めないので,健全な財政運営には歳出の抑制が必要に他なりません。
村としましては,今後も事業の優先順位をしっかり検討し,単独事業の後年度執行など,各分野で連携を図り計画的に予算執行するよう,努めてまいります。
歳入につきましても,財源に補助事業や有利な起債,ふるさと納税制度などを積極的に導入し,国の予算動向を注視しながら,地方交付税を適正に見込んで,財政調整基金で補い予算編成を行ってまいります。
これまでと同様,財政健全化を進めていくことは当然のことですが,目的財源としての基金の適時使用など,村民に必要な予算は積極的に活用するとともに,自主財源の確保に努めてまいります。
今年度以降の取り組みとして
今後の建設予定事業としましては,防災会館,給食センター,役場庁舎建設に加えて,空家改修事業や民間賃貸住宅の建設支援等,住宅不足解消へも取り組んでまいります。
さらに継続的な事業として,土砂処分場整備工事第1期工事を進めてまいります。建設にあたっては,将来的に財政を圧迫することがないよう,実施時期を見極めながら計画的に事業を進めてまいります。
むすびに
以上,令和7年度の村政運営に対する所信と施策について概要を申し述べましたが,村政運営につきましては,これからも村に住み続けたい,行ってみたいといわれる,村民の誇れる宇検村を目指し「宇検村(シマ)らしさ全開!」を合言葉に,職員一丸となって取り組んでまいりますので,議会議員並びに村民の皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げ,令和7年度の施政方針といたします。
村民の皆様,心をひとつに,笑顔あふれる宇検村(シマ)を築いていきましょう。
令和7年3月4日
宇検村長元山公知
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください